地震に強い家の特徴を徹底解説!揺れても安全な家に住もう
2023.10.02本ページはプロモーションが含まれています。

2011年に発生した東日本大震災は、人々に大きな衝撃を与えました。地震大国といわれる日本では、年々地震に強い家への関心が高まっています。
「地震が起きてしまったとき、建物が潰れてしまったらどうしよう…」このような心配を抱えている人もいるでしょう。
地震に強い家を建てるには、具体的にどうしたら良いのでしょうか。
今回は「住宅の耐震性」をテーマに、地震に強い家の特徴をさまざまな角度からご紹介します。
注文住宅の耐震性に関心をお持ちの方はぜひ参考にしてみてください。
目次
耐震性は安心・安全に暮らすために欠かせない要素
日本は地震が頻繁に起こる「地震大国」として世界にも知られています。
1995年の阪神淡路大震災では、新しい住宅でも耐震性が弱いものは倒壊し、多くの犠牲者を出しました。基礎構造が強固な家が津波に耐えうることが示されました。
このような経験から、日本では地震に強い家が重視されています。 地震はいつどこで起こるかわからないため、地震に強い家は日本で生活するための重要な安全対策となっています。
耐震性は、自分や家族の命を守るという最も基本的で最も重要な欠かせない要素なのです。
耐震強度を法律で定めた「新耐震基準」
もともと、日本では1950年に住宅の耐震基準が設けられていました。
しかし、1978年に起きた宮城県沖地震の被害を受け、その基準は見直され、新たな耐震基準が適用されることとなりました。これら二つの基準は以下のような違いを持っています。
- 旧耐震基準:震度5強程度の揺れで建物が倒壊しない。損傷しても補修すれば再び住める
- 新耐震基準:震度5程度の揺れではほとんど損傷しない。震度6強から7程度の揺れでも倒壊しない
阪神淡路大震災以降、上記の新耐震基準に
- ・木造住宅の基礎を地盤の強度に応じて設計する
- ・住宅の骨組みである建材の接合部分を強化する
- ・壁面を耐震化する
といった対策が加えられました。
3つのランクで表す耐震性能
新耐震基準は「震度6~7程度の地震で建物が崩壊・倒壊しない耐震強度」を最低ラインとしていて、「耐震等級」によって3段階にランク分けしています。
数字が大きくなるほど耐震強度が高くなり、各等級の強度は以下のように設定されています。
【耐震等級1】
震度5強の地震に耐え、震度6~7で損傷を受けても人命が損なわれないレベル。
【耐震等級2】
等級1の1.25倍の耐震性を持ち、学校や避難所と同じレベル。
【耐震等級3】
等級1の1.5倍で、病院や消防署と同じレベル
現在多くの住宅で【耐震等級3】が採用されています。
耐震構造には「耐震、制震、免震」の3種類がある
地震に強い家を建てる上で大切な「耐震構造」。
耐震構造には、以下の3つの種類があります。
耐震
耐震とは、建物の構造を地震の揺れに耐えられるよう強化することです。
具体的には、太く頑丈な柱や梁で建物自体を支えるような構造が耐震にあたります。
近年では柱を筋交いにつなぐ建材を入れたり、柱と柱をつなぐ壁を強度の高い素材に変えたりして、壁自体が揺れを吸収するような横揺れに強い構造が主流です。
制震
制震とは、地震の揺れを吸収する構造のことです。
制震構造の特徴として、壁の内部に地震エネルギーを吸収するダンパー(振動軽減装置)を設置する点が挙げられます。
揺れによって建物に生じる歪みをダンパーが吸収し、柱や梁、壁の損傷を最小限に抑えられます。また、制震構造の建物の中では地震の揺れを実際のものより小さく感じるので、安心感を得られる点もメリットです。
免震
免震とは、建物自体の揺れを軽減する構造のことです。
建物と土台(基礎)の間に積層ゴムやダンパーなどでできた免震装置を設置し、建物に伝わる揺れを抑えます。具体的には、地震時の揺れを通常の3分の1から5分の1にまで軽減することが可能です。
冷蔵庫やタンスといった重い家具が建物内で移動・転倒するリスクも少なく、もっとも安全で耐震効果が高いといわれています。
【関連記事】
シンプルな形の家は地震に強い
地震に強い家の特徴として、建物の形と高さがあります。
上から見たときに正方形や長方形になっているような、シンプルな形の家は地震に強いといわれています。
正方形や長方形の家は、家を囲む6つの面すべてが一体になっているため、揺れが発生した際に踏ん張って耐えることができます。
一方で壁面に凹凸があったり家の形がL字型だったりすると、地震の揺れが一点に集中しやすくなり、家が歪みやすくなってしまうのです。
また、3階建てのような縦に長い家は地震の際揺れやすいというデメリットも。平屋や2階建てなど低い高さの建物の方が地震に強い傾向があります。
地震に強い建物の構造はどれ?それぞれのメリット・デメリット
形と高さのほかに、建物の構造も耐震性に大きく関わってきます。
ここからは、鉄骨、鉄筋コンクリート(RC造)、木造のそれぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
鉄骨
鉄骨構造は、鉄骨の厚みが6mm未満の「軽量鉄骨」と鉄骨の厚みが6mm以上の「重量鉄骨」の2種類に分けられます。
どちらも揺れに強く倒壊しにくいのが特徴で、地震に強い構造といえるでしょう。鉄骨構造のメリットとデメリットを以下にまとめました。
鉄骨構造のメリット
【重量鉄骨】
・部材が工場で生産されるため品質にばらつきがない
・少ない柱で建てられ間取りの自由度が高い
・優れた耐火性・耐震性・耐久性を持つ
【軽量鉄骨】
・部材が工場で生産されるため品質にばらつきがない
・部材を工場で大量生産するため工期が短く済む
・軽いのに耐久性が高く、耐震性に優れている
鉄骨構造のデメリット
【重量鉄骨】
・気密性が高い分防錆処理をしないと鉄骨が錆びる
・通気性や断熱性が木造に劣る分夏は暑く冬は寒い
・強固な地盤が必要なため基礎工事や地盤改良のコストがかかる
・部材を大量生産できないので建築コストがかかる
【軽量鉄骨】
・気密性が高い分防錆処理をしないと鉄骨が錆びる
・通気性や断熱性が木造に劣る分夏は暑く冬は寒い
・熱に弱く、耐火性が高くないため耐火被覆の処理が必要
重量鉄骨も軽量鉄骨も耐震性は高いですが、錆びに弱く通気性が悪いというデメリットがあります。
鉄筋コンクリート(RC造)
鉄筋コンクリート(RC造)は、柱などの骨組みを鉄筋で組み上げて周囲を型枠で囲み、中にコンクリートを流し込む構法です。
耐久性の高さからマンションやビルなどに用いられる構造ですが、近年ではRC造の戸建て住宅も増えてきています。
鉄筋コンクリート(RC造)構造のメリットとデメリットを以下にまとめました。
鉄筋コンクリート(RC造)のメリット
- ・すべての重量を面で支え、高い耐震性を誇る
- ・耐火性が高く1000度の炎に数時間さらされても崩れない
- ・断熱性に優れていて空調効率が高い
- ・気密性に優れているので遮音性が高い
- ・耐用年数が長く、長持ちする(法定耐用年数は47年)
- ・曲線や円形も再現できてデザインの自由度が高い
鉄筋コンクリート(RC造)のデメリット
- ・強固な地盤が必要で、基礎工事や地盤改良のコストがかかる
- ・建築費用が高い(木造住宅の1.5倍~2倍ほど)
- ・水分を吸収する分結露やカビが発生しやすい
- ・外壁に経年による汚れが目立ちやすい
- ・増改築や取り壊しがしにくい
鉄筋コンクリート(RC造)は、もっとも地震に強い構造な一方、建築コストが3つの中で一番高いという特徴があります。
木造
木造は、戸建て住宅にもっとも採用される構造です。柱と梁によって建物を支えるのが特徴で、耐力壁を設けたり、各部材の接合部に金物を使ったりして耐震性や耐久性を上げることができます。木造構造のメリットとデメリットを以下にまとめました。
木造のメリット
- ・さまざまな間取りに対応できて自由度が高い
- ・壁を抜いたり部屋をつなげたりなど、増改築やリフォームがしやすい
- ・枠で建物を支えているので、窓口を大きくとれる
木造のデメリット
- ・職人の知識・技術・経験によって品質にばらつきがある
- ・現場での作業が多い分工期が長い
木造の住宅は3つの中では比較的建築コストが安く済みますが、耐震性は劣ります。耐力壁や接合金物の使用など、耐震性を上げるための工夫が必要です。
地震に強いハウスメーカーを選ぶ指標
地震に強いハウスメーカーを選ぶ際には、どのようなポイントを見ればよいか解説していきます。
地震に強いハウスメーカーを選ぶ際には、どのようなポイントを見ればよいか解説していきます。
3つのランクで表す耐震性能
耐震等級3が最高ランクで、もっとも強度に優れます。地震に強いハウスメーカーでは耐震等級3の住まいを扱うところも少なくありません。また、「長期優良住宅」の認定には耐震等級2以上が必要です。
耐震性能は「震度6~7程度の地震で建物が崩壊・倒壊しない耐震強度」を最低ラインとし、さらに地震に対する建物の強さを「耐震等級」によって3段階にランク分けしています。
数字が大きくなるほど耐震強度が高くなり、各等級の強度は以下のように設定されています。
| 耐震等級 | 強度の目安 |
|---|---|
| 耐震等級1 | 建築基準法で定められた最低限の耐震強度 震度5強の地震に耐え、震度6~7で損傷を受けても人命が損なわれないレベル |
| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の耐震強度。 学校や避難所と同じレベル。 |
| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の耐震強度。 病院や消防署と同じレベル |
現在多くの住宅で耐震等級3が採用されています。注文住宅を建てる際には、耐震等級の数字がいくつのものなのか、1や2なら問題ないのか住宅会社に確認しましょう。
耐震等級1では、倒壊はしないものの地震発生後にある程度の損傷を受けるリスクがあり、建て替えが必要となることも。災害後のことを考えると耐震等級2以上が安心できそうです。
ただし、地盤強度や地域によってリスクが異なるため、自分が住みたい場所がどれだけの地震リスクがあるかによっても家の地震対策は変わります。どの程度のレベルが必要なのか地震エリアや地盤情報と照らし合わせて考えていきましょう。
耐震等級は間取りや費用にも影響する
地震に強い家は丈夫なつくりにする必要がある以上、構造の制約がかかります。間取りにこだわりがある場合、自分の希望がどこまで組み込めるかよく確認しなければなりません。
一般的に、耐震等級が上がるほど工事費用も高くなるといわれています。
耐震性能を高めるには壁や柱を増やし、枠組みを補強するなど構造を強固にする必要があるため、その分建築コストが増すのです。
等級1の建物に対して等級2では2.5%、等級3では5%の上昇が目安です。加えて工事費用とは別に構造計算費や耐震等級の申請費・その他手数料などがプラスされるなど、全体にかかるコストが高くなる傾向にあります。

安心を最優先して費用が高くなっても等級を上げようと決めた方もいます。予算内でどこに費用をかけるべきかしっかり検討して選択しましょう。
セキスイハイムさんでは耐震等級「3」と等級の中ではもっとも頑丈なレベルの家が建てられるので、しっかりした地盤の上に丈夫な家を建てる、という私たちの希望がかなったかたちです。等級を上げると費用も増えてしまうのですが、安心には代えられないのでその点は納得して決めました。(ohagi26_さん)
https://minique.info/rev/1356/
実大耐震実験の有無
地震に強いハウスメーカーかは、実大耐震実験を行っているかどうかでも判断できます。
実大耐震実験とは、過去に起きた地震の揺れを再現し、建物の耐久性を調べるテストのこと。実験の結果は耐震性の高さを示す根拠となるので、地震に強い家を建てるハウスメーカーのなかには実験結果を公表しているところも多いです。
そのため、地震に強いハウスメーカーを選ぶ指標として、実大耐震実験の有無は確認しておきたいところ。
実験結果の情報には実験の内容や様子も含まれているので、チェックしてみましょう。
そのハウスメーカーならではの耐震・免震技術
大手ハウスメーカーの中には、独自の耐震・免震技術を開発しているところがあります。
住宅の基礎や構造部分から素材まで、さまざまな技術が研究・開発され、日々住宅の耐震性能を底上げしています。
独自の耐震・免震技術を持つハウスメーカーは、住宅の耐震性に注力している会社ともいえます。独自技術の内容を確認すると同時に、地震に強いハウスメーカー選びのひとつの指標として覚えておきましょう。
地震に強い家は「強固な地盤」と「頑丈な建物」が必要
耐震性を高めるために重要なポイントは、建物の基礎・構造と地盤です。
地震に強い家とは、「強固な地盤」の上に「耐震性能に優れた建物」がある家です。このどちらが欠けても耐震性の高い家は建ちません。
いくら建物が強固でも、地盤が弱いと建物が新耐震基準を満たしていても、震度6強~7程度の揺れで崩壊・倒壊してしまう可能性があるのです。
地盤には、建物の荷重をしっかり支えられる強度だけでなく、その土地が大規模地震の揺れに耐えられるかといった耐力も求められます。
脆弱な地盤は災害時に沈下や液状化する危険性がある
地盤が弱い土地は大規模地震が起こった際、沈下や液状化といった被害が出る危険性があります。
どんなに建物の耐震性が高くても、土地自体が脆弱では意味がありません。地震に強い家を建てるには、地盤の補強も重要なステップなのです。
弱い地盤の場合は改良工事が必要になります。工事の要否は事前調査で判断でき、元々地盤が強い土地ならば工事をする必要はありません。
地盤が弱い土地でも、建物に耐震補強工事を施すのと同じように地盤改良工事を行えば、建築に適したレベルに強度を上げられます。ただしその際は建物の費用とは別に地盤改良費用がかかることを覚えておきましょう。
【関連記事】
地盤改良工事は土地の特徴に適したものを選ぶ
地盤改良の工法にはいくつか種類があります。中でも多くの現場で採用されているのが、「表層改良工法」「柱状改良工法」「鋼管杭工法」の3つです。
どの工法を採用するかは土地の性質や使える重機の種類、建てる家の重量などに合わせて異なり、費用や工期もそれに伴い変動します。施工会社と相談して、土地の特徴に適した工法を選びましょう。
「土地を探しているけど、どこに相談すればいいかわからない」、「ネットで土地情報を調べてみたけど、なかなか良い土地が見つからない」という方には、希望の間取り、予算条件に合わせて指定地域の土地を探してもらえる「タウンライフ家づくり 土地探し特集」がおすすめです。
自分の要望にあった土地を、複数の不動産会社から提案してもらうことができます。地盤の硬さ、立地や周囲環境、水はけの良さ、日当たりなどに関しても相談できるので、より理想に近い土地が見つかります。「土地探しの悩み相談」や「いい土地の見極め方」など無料でアドバイスも受けられます。
さらに、ネットに載っていない未公開の土地も紹介してもらえるのもメリット。
土地と併せて間取りや見積も提案してもらえるので、より具体的なプランがイメージできますよ。
資料請求は、大きく分けて以下の3ステップ。所要時間は10分ほど、スマホのみで完了できます!
- ①希望する地域を選択
- ②家族構成や希望の間取りを選択
- ③家に関する要望を記入
③の要望に関しては、後から「イメージと違った…」ということを防ぐためにも、なるべく詳しく記入しましょう。
・土地の有無(所有している場合は広さ)
・家族構成
・駐車、駐輪スペースの必要性
・採光に関する要望(リビングを明るくしたいなど)
・検討中の間取り(吹き抜け、ウッドデッキなど)
・必要な部屋と位置(和室が必要、リビングは1階など)
・その他要望(プライバシーを重視したいなど)
【関連記事】
地震に弱い家の特徴とは?

地震に強い家の特徴を見てきたところで、次は地震に弱い家の特徴を3つご紹介します。
ビルトインガレージのある家
ビルトインガレージのある家は、1階部分の道路側に壁がほとんどありません。開口部を広くとると、その分建物を支える壁や柱の部分が減ってしまいます。
そのため家全体のバランスが崩れやすくなり、耐震性が弱くなりやすいのです。
ビルトインガレージのある家を建てる場合、地震に強い鉄骨住宅やRC造にするか、壁が少なくても強度を確保できる設計にすることをおすすめします。
吹き抜けのある家
リビングや玄関に大きな吹き抜けがある家は、柱や壁の量が少なくなる分、耐震性が弱くなります。
吹き抜けをつくる際は、重量鉄骨や鉄筋コンクリート(RC造)の家にする、耐力壁を用いるなど、耐震設計を考える必要があります。
旧耐震基準の家
1981年以前の「旧耐震基準」にのっとって建てられた家は、震度6~7程度の巨大地震が発生した場合、倒壊するおそれがあります。特に2階建て以上の木造家屋は倒壊のリスクが非常に高いです。
もし現在旧耐震基準の家に住んでいたとしても、壁や柱を補強する耐震工事をほどこせば耐震性を上げることができます。
自治体の中には、古い家屋の倒壊チェックや耐震工事の助成を行ってくれるところもあります。
万が一、震災が起きた場合は火災保険の申請をしっかり行いましょう
火災保険は、火災だけでなく風災などの自然災害による住宅の損害に対する保障を提供しています。
保険金を受け取るためには、被害箇所を報告し、必要な申請手続きを行う必要があります。
しかし、火災保険のは専門的な知識が必要な部分も多く、申請書類に事故原因などを正しく記載できずに、保険金の減額や一切下りなくなる可能性があります。
そんなときに便利なのが「火災保険申請代行サポート」です。
被害箇所の請求漏れを防ぎ、給付金請求に必要な書類の準備をサポートしてくれるため、簡単に、そして正確に申請をすることが可能です。
「火災保険申請ドットコム」は年1,000件の実績があり。プロフェッショナル集団が揃った火災保険申請サポートです。
・建物の状態を専門家にチェックしてもらいたい。
・どうやって火災保険請求したら良いか分からない。
・物件を修繕したいけどお金がない。
・コロナで将来先行きが不安なのでお金を確保したい。
・物件を売却する予定なので、できるだけお金にしたい。
など、火災保険に関しての様々な不安・疑問に親身になって答えてくれます。
完全成功報酬なので手出し0円(保険金が受給できなければ一切お金はかかりません)と良心的。
また、完全成功報酬に抵抗がある方は無料修繕も対応可能です。
地震保険も同時に調査・申請可能なので、是非お問い合わせだけでもしてみてくださいね。(火災保険とダブルで受給できるケースもあります。)
火災・震災が起きないのは一番ですが、自然災害なのでどうしても完全になくすことはできません。
災害が起きてから泣き寝入りしないよう、しっかりと備えておきましょう。
まとめ|実際に家を建てた人のリアルな声を参考に
地震に強い家の特徴や、耐震構造についてご紹介しました。
耐震性について改まって学ぶのに抵抗がある、なかなか時間がとれないという場合、もっと身近な感覚で情報を得ることができます。
必ずしも自分たちの条件にそのまま当てはまるわけではなかったり、今では改善されている可能性もあるので、体験談をチェックした後は住宅会社に改めて確認しましょう。
「さまざまなケースを知って情報を集める体験談」「今現在の正確な情報は住宅会社」というように、それぞれをうまく活用すると見解が広がるでしょう。
ミニークでは口コミを元にしたランキング形式で住宅会社を探せます。ぜひ家づくりに活用してください。
【関連記事】




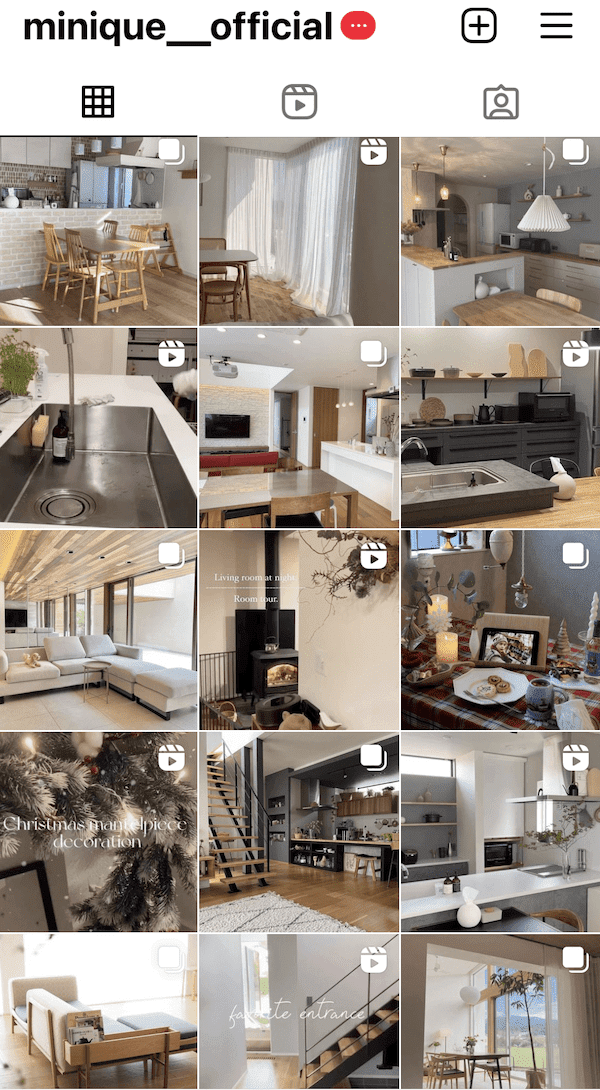
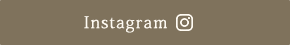

利⽤ユーザーの感想
満⾜度には個⼈差があるので流して⾒る程度かもしれません、、😅 ⼈が集まって作っていくものなので相性や信頼関係は千差万別ではないかと思います🤔 しかし、評価が低いと気になります。
2021/06/15
ハウスメーカーについては、2ちゃんねるのような無法地帯のようなサイトで好き放題評価されている情報が多かった。
酷評しているものが多く、本当の評価がよくわからなかった。
きちんと精査された情報サイトはありがたい。
2021/06/03
ステマが多い世の中になっているので、高い買い物だからこそ真実が知りたい
2021/05/19
やはり自分たちと同じような人たちがどれくらいいるのか、どのくらいの予算・場所・建てた会社は気になるし口コミ、書き込みは少なからず参考になると思います。
いいレビューなら、良かったと思いますし、あまり良くないレビューなら、やっぱりな。となりますし💦それで失敗しない家づくりを進める事ができればそれが一番だと思います。
2021/05/10
これから長いお付き合いとなるハウスメーカーや工務店のリアルな口コミを詳しく知ることができるため、利用したい🙆♂️また家族構成や建てた時の年齢なども自分と比べる時に役に立ちそう👍
2021/04/28
やはりレビューや口コミは、生のお客様の声なのでとても参考になる✨
表向きはいいことを発していても、蓋を開けたら違った!ということが少しでも減るのであれば、ぜひこういったサイトを活用した方がいいと思う...
2021/04/12
大体の世帯年収が書かれているとどの程度の年収であればどのくらいの価格の住宅を購入できるのか参考になる😃
2021/04/06
マイホームを立てる時、何も勉強しなかったので、建ったあとでInstagramなどを見て、あー!!こんなんすれば良かった!!って思う事が多々ありました😂😂😂
身近にこういう情報が見れるサイトがなかったものですから😂
2021/03/18
会社選びの参考とホームメーカー各社の比較検討の材料として、施主様のリアルな評価だけではなく、一人一人の家づくりストーリーが1つのコンテンツに込められているので、家づくりにおいて自分達は何を重視すべきかが確認でき、家づくりの参考になると思いました。
また施主の細かい情報(建設地・坪数・年齢・建物費用など)がきちんと書かれているので、自身の希望条件に合わせた情報が得られ、分かりやすくて良いと思います。
2021/03/07
家づくりでInstagramはかなり参考にしたのですが、その方々の細かい家づくりの話などにはすごく興味があったので、まとめられていると助かります🥰
2021/03/02