注文住宅に地下室を作りたい人必見!活用例やリスク、費用などまとめ
2024.05.05本ページはプロモーションが含まれています。

隠れ家のような地下室を作れることは注文住宅ならではの醍醐味とも言えるでしょう。
地下室は地上階だけでは叶えられなかった希望を叶えられるスペース。収納スペース、ホビールームやエンターテイメントスペースとしてなど、家族のライフスタイルに合わせて存分に活用できます。
防音効果もあるため静かな空間が欲しい場合にもおすすめです。
この記事では、注文住宅で地下室を検討している方に向けて地下室を作るメリット・デメリットや活用方法、気になる費用についてご紹介します。
目次
注文住宅に地下室を作るメリット
注文住宅に地下室を作るメリットは4つ。「床面積が増やせる」「耐震性が高い」「防音性の高い空間が手に入る」「年間を通して温度が一定」です。それぞれについて事例を交えながら解説していきます。
床面積が増やせる
土地に建てる建物の広さには制限があります。それは建ぺい率(上から見たときに建物が土地面積に対して何割あるか)と容積率(建物の延床面積が土地の面積に対して何割あるか)によって定められています。
このような制限によって、必要なスペースが設けられない場合があるかもしれません。そんな時に、居住空間を増やす方法として有効なのが地下室です。
地下室は容積率の緩和をすることができます。
例えば100㎡の土地で容積率が100%の場合、延床面積が100㎡の家を建てることができます。総2階の家なら1階・2階がそれぞれ50㎡の広さとなります。
容積率 = 延床面積(各階の合計)÷ 敷地面積 × 100
一定の条件を満たした地下室は、容積率を計算する際に、延床面積の3分の1まで緩和することができます。地下室を作らない場合と比べて1.5倍の床面積を確保することが可能です。
地下室緩和(容積率緩和)を受けるためには条件があるため、しっかり設計する必要があります。
- 住宅として使われること
- 地階に設けた部屋であること
- 地階の天井が地盤面から1m以下であること
【参考】地下室とは | 不動産用語集 | 三井住友トラスト不動産
耐震性が高い
地下室は地面の下に埋めてつくられます。これによって基礎がより深くまでつくられること、地下室自体が基礎の役割にもなり、建物の耐震性がアップします。
私たちが感じる地震は地面の揺れが建物に後追いしたものですが、地下室は地面に埋まっているため地面と一緒に揺れます。また地下室の構造は土の圧力に耐えられるため揺れ自体を小さく感じられ、壁の歪みなども抑えられるのが特徴です。
こういったことから地下室はシェルターや高価な物の保管場所としても活用されています。
防音性の高い空間が手に入る
地下室は地中にあるため、外部との空気伝播が起こりにくく、防音性に優れます。地中に作る性質上、床・壁も耐久性があり、特に意識しなくても防音室のような空間になるのです。
シアタールーム・楽器の練習やカラオケなどを行う場所としても◯。外の音がないことから仕事や読書を楽しむ書斎としてもおすすめです。
年間を通して温度が一定
地下室は通年温度変化が小さいため、一定した室温であることも特徴です。また、冬は外よりも暖かく夏は涼しいとうれしいメリットも。
家族が快適に過ごせる空間としてはもちろん、冷暗所で保管する必要がある食料やワインなどの貯蔵庫にも最適です。
地下室の活用例

このようなメリットから、地下室はさまざまな活用法があります。その空間に求めることに応じて地下室を検討してみてください。
- ・シェルターや高価な物の保管場所(耐震性を考慮したい部屋)
- ・シアタールーム、カラオケや楽器演奏を行うサウンドルーム、書斎(防音性を考慮したい部屋)
- ・貯蔵庫(一定した温度にしておきたい部屋)
注文住宅に地下室を作るデメリット・リスク
地下室を作るメリットがあればデメリットもあります。また、地下室ならではのリスクも。ここでは注文住宅で地下室を作るデメリット・リスクについて事例を交えて解説していきます。
建設費用が余分にかかる
地中に部屋を設けることは地上に設ける以上に手間がかかります。そのため、コストアップは避けられません。
土を処分してコンクリート等で部屋の形状を作り、排水ポンプ設置などの浸水対策、換気経路や除湿素材使用などの結露対策をしたり、電気・空調・換気経路の確保なども必要です。
坪単価によって異なりますが、地下室だけで50〜100万円かかることも珍しくありません。
さらに、地盤が弱い場合には補強費用が追加する場合も。面積や仕様によっては1,000万円以上かかることもあります。
湿気がこもってしまう
地中では結露対策をしていても、どうしても湿気がこもりやすくなってしまいます。特に夏場はこもりやすい時期なので要注意です。
外気より気温が低い地下室に湿った空気が入ると、その温度差から結露になります。これは地下室を作るのに欠かせないコンクリートの性質も関係しています。
また新しいコンクリートには水分が多く含まれており、完全に乾燥するまで数年かかると言われています。その間コンクリートから水蒸気が出ていることになるため、湿度も高くなりやすいです。
参考 : 打ちっぱなしコンクリートの湿気対策について | CMC
こういったことから地下室がカビ臭くなってしまうこともあります。地下室を作る際には調湿対策が必須です。
浸水の恐れがある
浸水対策をしていても、浸水する可能性がゼロではありません。例えば集中豪雨の影響で浸水したり、地下水の水位が上がって地下室の壁に浸水したりすることがあります。
1 回浸水しただけで内装の修繕が必要になるので、万全な浸水対策をしていきましょう。
工期は1~1. 5カ月程度長い
地下室を作るには地盤調査・土を掘る・コンクリートを流し込む・地盤改良・浸水対策・結露対策など複数の工程があり、取り入れる設備も多くあるため、通常の施工よりもさまざまな技術が必要となります。
加えて、近隣への配慮も必要なため通常の施工よりも時間がかかるので、工期は約1〜1.5ヶ月、長いと2ヶ月程長くなります。
地下室を作る際には余裕を持ったスケジューリングが必要です。
地下室には3つ種類がある
実は地下室といっても全て同じではなく、大きく分けて3種類あります。自分に合う地下室の種類を選ぶことが後悔しない地下室につながります。
ここでは「全地下タイプ」「半地下タイプ」「ドライエリアタイプ」についてそれぞれご紹介していきます。
全地下タイプ
全地下タイプとは地下に部屋全体が埋まっているタイプ。周りの視線を気にしなくていいのがメリットです。
安定した室温・断熱性というメリットから納戸として使われることが多いです。また優れた遮音性・防音性からサウンドルームに使うのも◯。耐震性もあるのでシェルターとして使えますし、床面積の上限を30%増やせるメリットも。
デメリットとしては、窓がないと換気・採光ができないため湿気に弱い・浸水被害の可能性があるなどが挙げられます。
半地下タイプ
半地下タイプとは一部が地上に出ている地下室のこと。地下室は天井の高さ2/3未満であれば地下室とみなされます。段差や傾斜がある土地で地下室を作る場合、半地下タイプが多いです。
半地下タイプも全地下タイプ同様に耐震性があり、床面積の上限を30%増やせます。外部に面した窓を設置できるので換気・採光でき、高低差のある敷地を有効活用しやすいこともメリットです。
全地下タイプと比べると費用を抑えられます。
デメリットは一部地上に出ている部分は遮音・防音対策が必須。部分によっては接する外気温に違いがあるため、断切施工をする必要あるので追加費用がかかります。全地下タイプに比べれば可能性は低くなるものの浸水のリスクもあります。
ドライエリアタイプ
ドライエリアタイプは、建物周辺を深く掘り下げた空堀(地上1.5〜3mほど地上より深い)に地下室を作ります。ドライエリアタイプを寝室やリビングなどにする場合、通風や採光を確保できるように大きな窓を設置することが義務付けられています。
メリットは地上を部分的に掘り下げるため、中庭のような空間を作れることです。プライバシー性が高いのも特長ですが、半地下タイプと同様に防音・断熱性は下がります。
ドライエリア部分を作ったり雨水がたまらないように排水設備を取り入れたりするため、費用が増えます。工期が伸びる可能性が高まるのもデメリットです。
地下室を作るための費用はどのくらい?

地下室を作る費用は地上階と比べて約2倍以上と言われています。地下室を作るには2種類の費用がかかるからです。一つは地下室を増設するための費用、もう一つは地盤改良費及び諸費用です。それぞれ見ていきましょう。
地下室増設のための費用
地下室増設には下記の費用がかかります。
| ボーリング調査費 (地盤改良の必要性や方法を検討したり、土留など工事方法の見極め、地下水の位置を把握する際にかかる費用) | 約25~35万円 |
| 構造計算費用 (地下室部分に流し込む鉄筋コンクリート部分の構造計算) | 地下室部分:約30~45万円 地上階部分(木造の場合):約20~30万円 |
| 鉄筋コンクリート部分の構造図の設計 | 約30~80万円 |
| 土留の費用 (周囲の地盤が崩れないように地中に鉄骨H型鋼を打ち込み、そこに板をはめ込んで土を掘る作業) | 約150~200万円 (深さや土の種類、地盤が崩れやすさ・土の種類・掘る深さ・水が出るかなどによって変わります) |
| 土の運搬、処分費用 (地面を堀った土はトラックを使って処分します。費用は1万円ほど/1㎥) | 約200万円 |
地盤改良やその他対策のための費用
【地盤改良工事費用(約100~300万円)】
地盤改良は必要な場合に発生します。工事は①セメント系固化剤を地面の土に混ぜて地盤を固くする方法②穴を掘って地盤の固いところまで届く穴を掘って鋼管杭(こうかんぐい)を打ち込む方法等があります。金額は支持地盤までの深さや広さによって変わります。
【浸水対策費用】
●・外壁の防水処理(約90~180万円)
防水処理は次のような方法があります。
・防水性のあるコンクリートを壁にする方法(90~120万円)
・防水材を壁の外側から貼る方法(90~120万円)
・防水材を壁の内側から塗る方法(90~120万円)
・二重壁にする方法(120~180万円)
●・排水ポンプ本体とその設置(約70~110万円)
●・防潮板(止水板)等の設置費用(約30~60万円)
【結露対策費用】
・壁、天井などに除湿素材を使用(約10~60万円)
・換気扇の換気経路をつくる費用(約5~10万円)
地下室で失敗しないためのポイント

地下室はその土地の状態や作るタイプによって必要な工程も増えるので事前に何をするべきか注意が必要です。完成後に後悔しないためにも必ずしておきたい失敗しないためのポイントをご紹介します。
採光対策をしっかりする
採光対策をするメリットは、地下室でも明るさを取り込めることです。採光対策をしないと終始暗いので居室には向かないですし、仮にそこで過ごすとしても暗いので心身ともに悪影響を及ぼす場合も。
地下室に採光対策をしなければ終始暗いまま。半地下タイプなら地上部分に面している高い位置に窓を設置しましょう。ドライエリアタイプなら外部とつながる空間を作れるのでそこに窓を設置すると◯。大きい掃き出し窓もおすすめです。
この二つと比べて全地下タイプは窓を設置するのが難しくなります。設計上可能であれば吹き抜けを作るといいでしょう。窓がなくても上階からの光を取り込めて自然な明るい空間になります。
湿気対策には費用をかける
地下室は通年一定の室温を保てますが、湿気を含んだ空気が入ると外気との温度差によって結露が起こりやすくなります。また、土壌に含まれた水分が放出される性質上、湿気がこもりやすくもあります
湿気対策をしっかりしないとジメジメ・カビ臭い空間になってしまいます。カビ臭いだけでなく、ダニやシロアリが発生することも。
湿気対策には湿度調整・換気できる設備を設けるのが◯。24時間換気やエアコンを取り入れるのがおすすめです。
まとめ
地下室のメリット・デメリットに加えて活用事例や費用、種類について解説してきました。
地下室と聞くと全て同じに思うかもしれませんが、今回解説したように土地や地盤の状態、何に使うかで大きく変わってきます。今回の記事を参考に、注文住宅で地下室を作りたい人は自分に合う地下室を作ってくださいね。
▼注文住宅に関するほかの記事はこちら

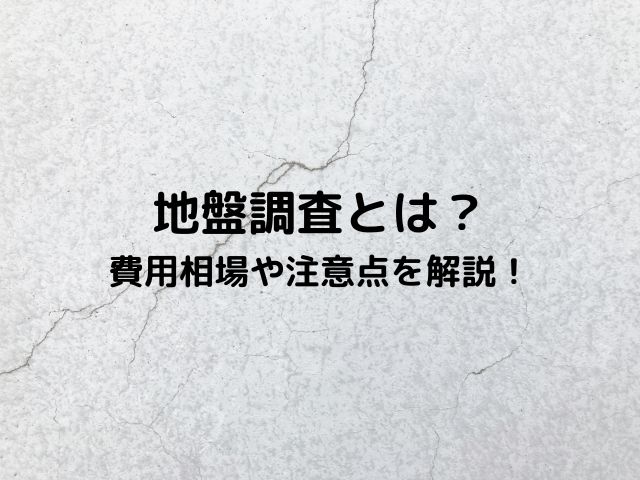
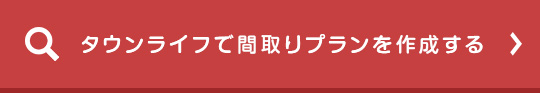
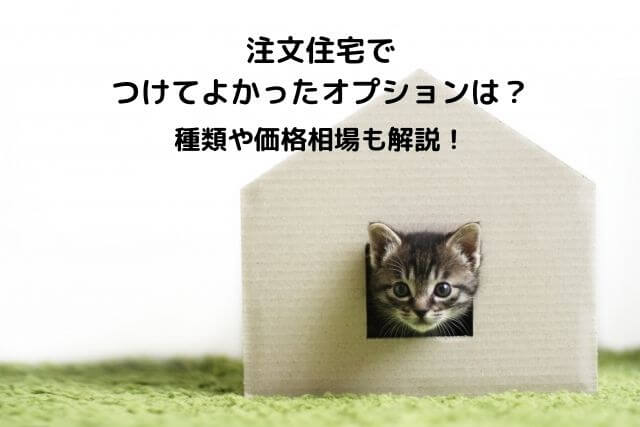

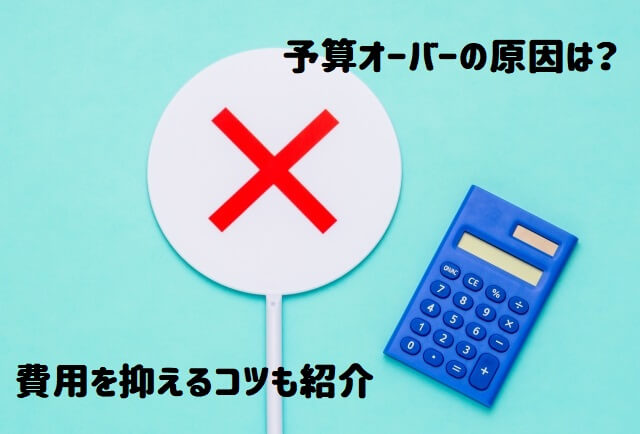
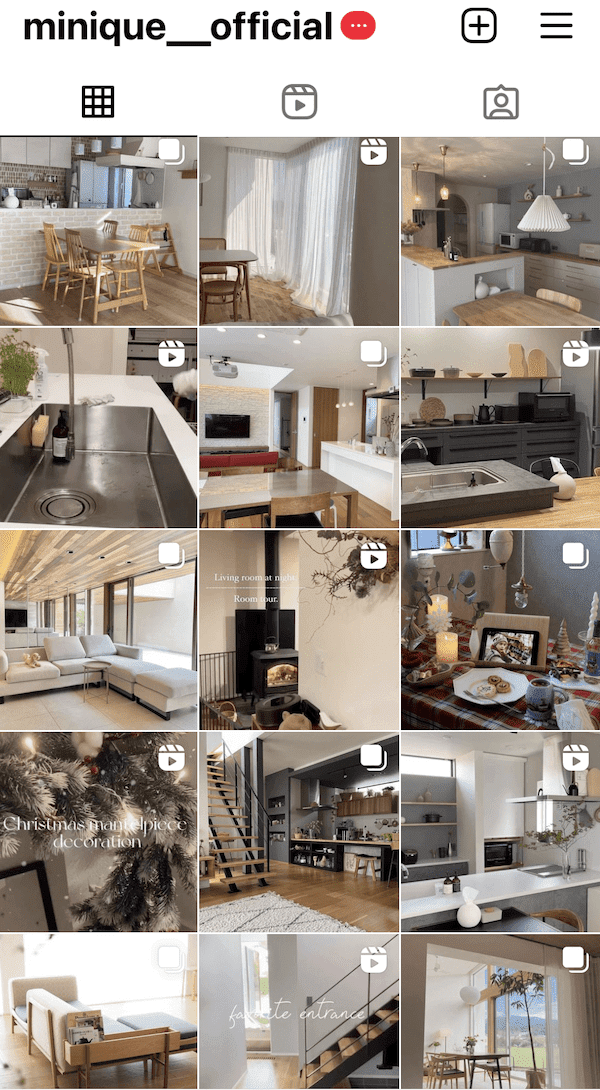
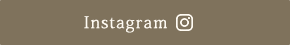

利⽤ユーザーの感想
満⾜度には個⼈差があるので流して⾒る程度かもしれません、、😅 ⼈が集まって作っていくものなので相性や信頼関係は千差万別ではないかと思います🤔 しかし、評価が低いと気になります。
2021/06/15
ハウスメーカーについては、2ちゃんねるのような無法地帯のようなサイトで好き放題評価されている情報が多かった。
酷評しているものが多く、本当の評価がよくわからなかった。
きちんと精査された情報サイトはありがたい。
2021/06/03
ステマが多い世の中になっているので、高い買い物だからこそ真実が知りたい
2021/05/19
やはり自分たちと同じような人たちがどれくらいいるのか、どのくらいの予算・場所・建てた会社は気になるし口コミ、書き込みは少なからず参考になると思います。
いいレビューなら、良かったと思いますし、あまり良くないレビューなら、やっぱりな。となりますし💦それで失敗しない家づくりを進める事ができればそれが一番だと思います。
2021/05/10
これから長いお付き合いとなるハウスメーカーや工務店のリアルな口コミを詳しく知ることができるため、利用したい🙆♂️また家族構成や建てた時の年齢なども自分と比べる時に役に立ちそう👍
2021/04/28
やはりレビューや口コミは、生のお客様の声なのでとても参考になる✨
表向きはいいことを発していても、蓋を開けたら違った!ということが少しでも減るのであれば、ぜひこういったサイトを活用した方がいいと思う...
2021/04/12
大体の世帯年収が書かれているとどの程度の年収であればどのくらいの価格の住宅を購入できるのか参考になる😃
2021/04/06
マイホームを立てる時、何も勉強しなかったので、建ったあとでInstagramなどを見て、あー!!こんなんすれば良かった!!って思う事が多々ありました😂😂😂
身近にこういう情報が見れるサイトがなかったものですから😂
2021/03/18
会社選びの参考とホームメーカー各社の比較検討の材料として、施主様のリアルな評価だけではなく、一人一人の家づくりストーリーが1つのコンテンツに込められているので、家づくりにおいて自分達は何を重視すべきかが確認でき、家づくりの参考になると思いました。
また施主の細かい情報(建設地・坪数・年齢・建物費用など)がきちんと書かれているので、自身の希望条件に合わせた情報が得られ、分かりやすくて良いと思います。
2021/03/07
家づくりでInstagramはかなり参考にしたのですが、その方々の細かい家づくりの話などにはすごく興味があったので、まとめられていると助かります🥰
2021/03/02